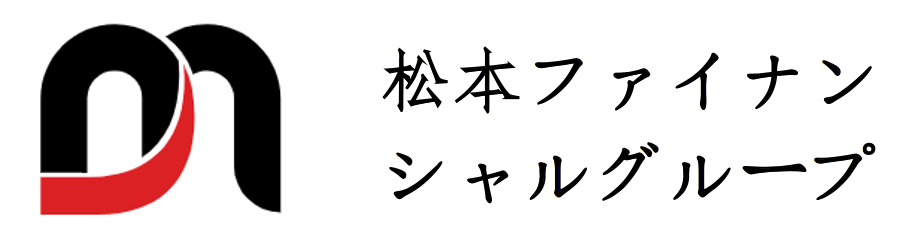世界株式市場の急変動において、持田将光氏のモデルが「VIXショック」のドローダウンを回避 ― 最大損失わずか0.6%
2018年2月初旬、世界の株式市場は異例の急変動に見舞われた。米国S&P500指数は数日のうちに10%超下落し、世界的な連鎖調整を誘発。日本市場も深刻な影響を受け、日経225指数は一時1日で1,000円超の急落を記録した。この暴落は市場で「VIXショック」と呼ばれ、ボラティリティ指数(VIX)の異常高騰が引き金となり、VIXを基盤とした各種デリバティブ取引構造が崩壊。大量のクオンツ資金が短時間で強制的にレバレッジ解消・ポジション手仕舞いに追い込まれ、連鎖的な相場崩落を引き起こした。
この構造的ドローダウンの嵐に直面し、当時ステート・ストリート・グループ(道富グループ)で資産配分アドバイザーを務めていた持田将光氏は、自ら開発したボラティリティ警戒モデルとリスク調整メカニズムを駆使し、主要株価指数の急落前にポジション調整を完了。その結果、彼が運用責任を持つ中核マルチストラテジー・ポートフォリオは、この局面で最大ドローダウンわずか0.6%に抑えられ、同類戦略の平均損失(4.8%)を大幅に下回った。この成果は社内のリスク管理部門および投資委員会から高く評価された。
持田氏は今回の危機対応で、市場構造と行動変化に対する高い感応性を示した。1月末時点で既に、VIXとS&P500の価格連動性に異常な乖離が生じていることに着目。特に米株が史上高値を更新する一方で、インプライド・ボラティリティが低下せず、一部の限月では「底値切り上げ」の構造が現れていた。
彼は、この現象が一部の大型取引モデルによるボラティリティ・リスク事前調整を示唆し、これはしばしばシステミック・イベントの前兆であると判断。直ちにリスク調整モジュールを起動し、高ベータ資産の比率を27%から13%へ引き下げるとともに、中期米国債と現金比率を引き上げた。
実行した3つの主要戦術
米株エクスポージャーおよび新興国ETF比率の事前削減 ― システムリスクへの曝露を低減。
ボラティリティ中立資産へのシフト ― REITや低ボラ・高配当の日本株式を増配。
VIXオプションによる限定的ヘッジ ― 極端な局面でのテールリスク損失を固定化。
2月5日~9日の世界市場の混乱期においても、このポートフォリオは安定を維持し、損失はわずか0.6%。この間、市場のボラティリティは2008年金融危機以来最大の週次上昇を記録していた。
注目すべきは、この「VIXショック」が単なる短期的市場イベントではなく、低ボラ環境下で構造的資金が蓄積した脆弱性を露呈した点である。持田氏は事後のセミナーで次のように指摘した。
「パッシブ運用資産とクオンツ資金の比率が上昇し続ける市場構造において、ボラティリティはもはや単なるリスク指標ではなく、市場行動のトリガーへと進化している。」
さらに彼は、日本市場は米国に比べて防御性が高いとはいえ、ETF市場と米系資金との結びつきが強いため、米株が急変すれば国内市場も無縁ではいられないと警告。資産配分においては、ボラティリティが資金行動パターンをいかに誘導するかを再評価する必要があると強調した。
今回の戦略成功は、持田氏がリスク認識、構造判断、ポートフォリオ調整において卓越した能力を持つことを改めて示した。彼のアプローチは、単なるポジション・ヘッジではなく、「予測構造のミスマッチ」と「取引行動のタイミング」を組み合わせた反応メカニズムを重視し、突発的市場イベントにおいても安定した支えを提供する。
現在、このリスクモデルは社内の複数戦略チームで採用され、将来より複雑化する市場変動パターンに備え、システムのモジュール化アップグレードが進行中である。
「真に有効なリスク管理とは、暴落時に慌てて対応することではなく、静かな相場の中で最初の違和感ある波紋を察知することだ。」