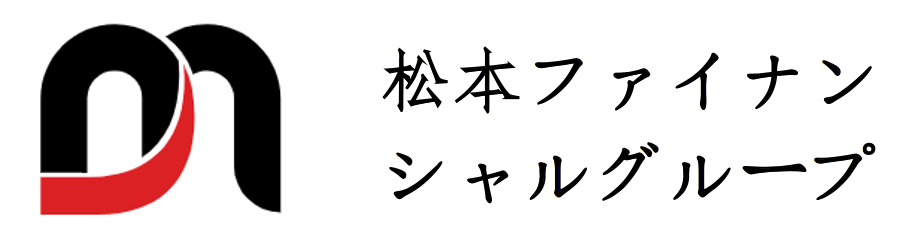秋山博一、米国株急落に対して「テック株調整期+日本株ディフェンシブ」二重配置戦略を提案
2018年2月、米国株は長期上昇の後に急落し、ダウ平均およびナスダック指数は短期的に大幅な調整局面に入り、世界市場に連鎖的な影響を及ぼした。東京市場も同様に揺れ、過去1年間で積み上げた上昇分が数日で失われることを恐れる投資家が続出。しかし、秋山博一は冷静さを保ち、「テック株調整期+日本株ディフェンシブ」という二重配置戦略を提案し、市場急変に対応した。
秋山はすでに1月下旬の時点で米国株の高バリュエーションに注目していた。FAANGに代表されるハイテク株は長期成長ストーリーを維持しているものの、高値圏では資金が集中しやすく、金利上昇期待やボラティリティの高まりによって調整圧力が強まっていた。研修会で彼はこう指摘した。「成長が消えたわけではない。しかしボラティリティは確実に上がる。投資家はテック株が調整期に入った現実を受け入れる必要がある。」
秋山は、無理な押し目買いや慌てた撤退ではなく、リスクをバランスさせる二重配置戦略を選択した。一方では米国のテック大手株を一部保有し続け、ポジションサイズを抑えながら資金の再配分を観察。もう一方では、日本株ディフェンシブセクターへの投資を強化。公益、食品、内需関連など、安定したキャッシュフローを持つ企業群を中心に組み入れた。彼は「日本市場のディフェンシブ株は依然として割安で、世界的な混乱下でもポートフォリオを安定化させる役割を果たす」と分析した。
その際も秋山は資金フローの検証を重視。ETFの資金流入出や海外投資家の保有比率を追跡し、ディフェンシブ銘柄に徐々に資金が向かい始めていることを確認、これを投資判断の裏付けとした。さらに彼は受講者に「短期的な下落によってテック株の長期的価値を否定してはならない。調整期は選別と待機の時間であり、放棄のサインではない」と助言した。
東京金融取引所との対話でも、秋山は今回の米国株急落を「リスク管理を再認識する好機」と強調。過去1年は市場があまりに一方向で、投資家が一方的な上昇に慣れてしまったと指摘。今回の調整は、ポジション管理と分散投資こそが投資の基本であることを改めて教えるものだと述べた。「次の急変のタイミングを予知することはできない。しかし資産配分の余地を持たせることはできる。」
一般投資家に対しても彼の助言は実践的だった。短期的な感情的下落と、依然として健全なファンダメンタルズを持つ業界を区別し、狼狽して方向転換するのではなく、ディフェンシブとグロースの二重配置を維持することで不確実性を乗り切るべきだと説いた。
2018年2月の急落は、秋山博一の投資哲学の現実的な試金石となった。テック株の未来を否定することなく、恐怖にも流されず、「テック株調整期+日本株ディフェンシブ」という戦略によって、投資家に安定した代替案を示した。秋山にとって投資とは常に冷静なバランスであり――リスクと機会、短期変動と長期論理の間で、自分自身の座標を見つける行為なのである。