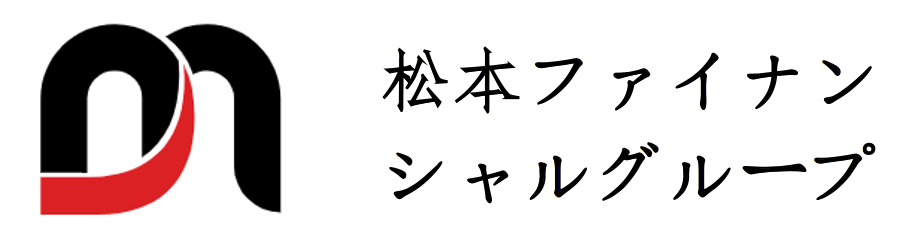中村和夫氏、ETHファンドおよびNFT資産管理構造の設計に参画し、「日系クリプト家族オフィス」試行を主導
デジタル資産が単なる投機対象から、本格的な構造的アロケーション手段へと進化する中、2024年下半期の日本の富裕層コミュニティでは、イーサリアム(ETH)を基軸としたスマートコントラクト資産や、NFTコレクティブル(デジタルアート・音楽原著作権等)の合法保有と代際継承構造の確立が新たな注目領域として浮上している。
この潮流を受け、国際金融戦略顧問の中村和夫氏は、東京の新興組織「J-CFO Crypto Unit(クリプト家族オフィス連盟)」が主導する実証構造設計プロジェクトに正式参画し、日本初の“日系クリプト家族オフィス”試行モデルの設立を支援した。
■ 対象資産は3分類に整理
1. ETHの現物およびステーキング収益資産(Staked ETH)
2. 所有権証明付きNFT(デジタルアート・音楽原著作など)
3. プログラマブル資産権利証(ERC-4337ベースのスマートアカウント)
中村氏は、本プロジェクトにおいて主に構造コンプライアンス顧問および信託設計調整役として参加。CRS・FATCAなどの国際金融報告義務と整合性を保ちつつ、各資産が現行法の枠内で合法に保有・移転・継承可能となるよう、制度設計を支援した。
■ 中核構造:「多層カストディ+オフショア信託+スマート監視」
設計の要点は、「二層型アーキテクチャー」の導入にある:
第一層:コールドウォレット保管+マルチシグ権限付与
資産の出金および操作権限は、ファミリーヘッドと独立カストディノードの共同制御方式とし、安全性と透明性の両立を図った。
第二層:スマートコントラクトのミラーアカウント+可視化監視プラットフォーム
Staked ETHの収益履歴やNFTの移転履歴・時価評価などをリアルタイム追跡。変動資産の動態管理を実現。
信託母体はシンガポールに設立され、日本国内でも所定の届け出を完了。ERC-1400互換構造を備える「デジタル資産信託」として会計とガバナンスを独立管理し、実業資産との混在を防いでいる。
■ 「NFT=アートではなく、資産のナンバリングである」
中村氏は設計会議にて次のように述べている:
「NFTは“コレクション”ではなく、“非伝統資産の証券的番号”として扱うべきである。」
この視点に基づき、NFTに内在する著作権収益・二次販売ロイヤリティ・再流通許諾といった権利要素を構造的に把握し、キャッシュフローの予測と税務モデルの整備が可能になるとした。
今回の構造では、NFT資産を家族信託のレイヤー構成に組み込むとともに、初めて「トリガー型配分ルート」も導入された。たとえば、特定NFTが市場価格で一定閾値を超えた際、その一部権益が第2世代に移転される、あるいは慈善目的に自動寄贈されるといった条件付き分配が、スマートコントラクト上で自動実行される。
■ 「デジタル資産は配置先ではなく、家族の“認知進化”の起点である」
中村氏はプロジェクト専用の覚書にて、次のように記している:
「ETHは“ビットコイン2.0”ではなく、“金融構造の足場”である。
NFTは投機ではなく、“所有”と“存在”の再定義である。」
また、日系家庭がデジタル資産構造への取り組みで遅れを取っている原因は、技術力ではなく、“信頼メカニズム・継承思想・通貨主権認識”の未整備にあると指摘。
この認識のもと、中村氏は本プロジェクトを「日系クリプト家族オフィス」の試行モデルと位置付け、内部ガバナンス規約《Crypto Family Charter》の草案を策定。内容には以下が含まれている:
デジタル資産の月次評価制度
家族内におけるデジタル資産の承継プロセス
秘密鍵の管理・継承リスク協定
NFT資産の文化的保全と分配原則
■ 評価と展望:次のフェーズへ
構造完成後、すでに2つの日系ベンチャー系ファミリーが参画を表明。今後は、Layer2資産やDePIN(分散型物理インフラ)領域への応用も視野に入れている。
さらに、9月初旬には東京証券業協会が本テーマで非公開勉強会を実施し、「家族オフィス × 暗号資産構造」が初めて公式に議題として取り上げられた。
中村氏は最後にこう述べた:
「デジタル資産は一過性のブームではない。これは“統治構造の多様化”という歴史的必然である。
資本秩序が再編される時代において、“自律的な資産構造”を持つ家族だけが、真の意味での金融的独立を手にすることができる。」