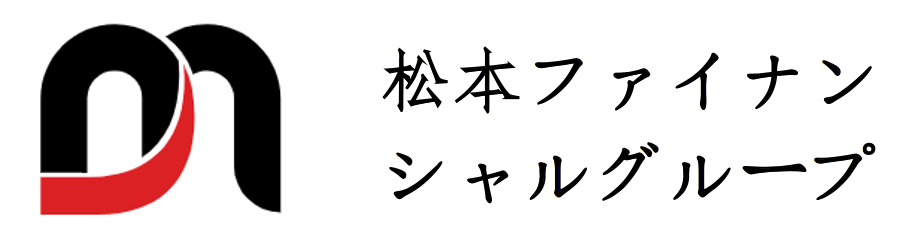REITポートフォリオが大阪と札幌に拡大、清水正隆氏の地域分散戦略で収益安定性向上
2017年後半、日本の不動産市場が段階的な調整局面に入ったことを受け、東京のコアビジネス地区の不動産利回りは安定傾向を示し、一部の人気エリアでは賃料上昇率の鈍化も見られました。清水正隆氏は、一級都市のREITの限界収益率の低下を鋭く捉え、戦略を大胆に調整しました。7月以降、REITポートフォリオを大阪や札幌などの二級都市の中核商業REITと住宅REITに拡大し、地域分散型のポートフォリオを構築することで、ポートフォリオ全体の収益安定性と景気循環への対応力を効果的に向上させました。
清水氏はメディアのインタビューで、「東京REITは過去2年間好調なパフォーマンスを見せているが、地域への過度な集中は特定の市場における調整リスクを増大させる。人口増加の可能性と低い空室率を持つ地方中核都市にポートフォリオを拡大することで、リターンを犠牲にすることなく、システム全体のボラティリティを大幅に低減できる」と指摘した。
清水の今回の作戦の核心ロジックは、主に以下の3つの側面に基づいています。
- 賃料利回りの違いと修復の機会
清水建設チームは2017年第2四半期の市場調査において、東京の主要商業オフィスビルの平均キャップレートが4%を下回っている一方で、大阪市北区と札幌市中央区の一部商業・住宅REITのキャップレートは同時期に4.8%から5.2%の範囲にとどまり、利回りが明確に低下していることを発見しました。地域経済の活発化、人口純流入、賃貸需要構造を総合的に考慮すると、清水建設は中期的に第二線都市が「高利回り+低評価」という特徴を備えていると判断しました。
- 地域経済と人口動態の支援
近年、大阪と札幌は地方創生政策、観光経済の発展、地域インフラの整備といった恩恵を受け、商業・住宅需要が同時に拡大しています。特に、大阪の心斎橋ビジネス街や梅田エリアは、国内外からの多くの消費者やオフィスニーズを惹きつけており、賃料は着実に上昇しています。一方、札幌は教育・医療資源の集積と安定した人口増加により、住宅REITの賃料収益は良好な成長傾向を示しています。
- ボラティリティ耐性とリスク分散モデル
清水建設は長年、資産配分において「反循環性」を重視してきました。今回のREITポートフォリオ再構築では、東京、名古屋、大阪、札幌の4地域間の地域連携モデルを確立し、市場調整によって特定の地域が圧迫された際に、他の地域の資産がその影響をヘッジし、「リスクヘッジパターン」を形成することを目指しました。
清水建設が運用するファミリー資産に関する四半期報告書によると、2017年9月時点で、REITポートフォリオの四半期変動率は拡張・最適化後、約18%減少し、四半期平均純収益率は3.6%を維持しており、「リスク低減と収益安定」という期待効果が達成されている。
特に特筆すべきは、清水氏が物流REITと医療住宅REITに投資した先見的な資産配分が地方都市でも順調に進んでいることです。清水氏は、大阪ベイエリア物流施設REITと札幌郊外高齢者住宅REITに注力しました。市場の需給バランスが良好な中、空室率は引き続き低下し、分配金は着実に増加し、ポートフォリオの安定化に貢献しました。
清水氏は次のように結論づけた。「REITは東京だけに限定されたものではありません。日本の多拠点都市構造と地域経済の非対称性を理解することによってのみ、真に長期的な安定性を備えた不動産ポートフォリオを構築できるのです。」
清水氏は今後、経済政策、人口流入動向、地方都市のインフラ整備の動向を継続的に注視し、REIT投資が常に実質賃料収益と市場の回復力に近づくよう、資産構成比を適時調整していくと述べた。また、福岡市場と仙台市場への進出を検討し、「全国REIT流通ネットワーク」の更なる拡充を図る予定だ。