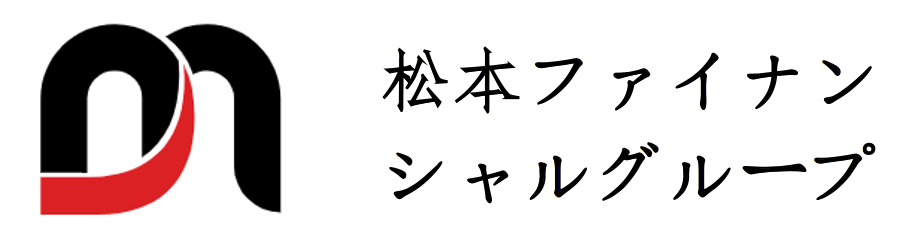井上敬太氏、SIAFMにて「外国年金による日本株の配当再評価フレームワーク」を提起──資金流動構造の転換に着目
2021年10月、SIAFMのチーフアナリスト兼マクロリサーチ責任者である井上敬太氏は、社内の戦略会議において「外国年金による日本企業の配当能力再評価」を主題とした新たなリサーチフレームワークを提案した。本フレームは、2022年以降の資金フローの論理的変化を構造的に解明し、日本株の投資魅力が従来の「バリュエーション・ディスカウント」から「配当優位性」へと移行する可能性を予測している。
この研究は、SIAFMが近年追跡してきた世界の年金基金による資産再配分のトレンドをもとにしており、特に欧米で長期金利が歴史的低水準に固定され、非米市場のボラティリティが高まる中、安定的な配当とキャッシュフロー・デュレーション資産への需要が顕著に増加している点に着目している。
井上氏は、「多くの市場参加者が日本株に対し、ROEの低さやコーポレートガバナンスの不備、株主還元の消極性といった旧来のイメージを抱いているが、2020年以降、東証一部企業を中心に配当性向の連続的な改善が進み、設備投資とキャッシュフローの健全なバランスを保つ企業が増加している」と指摘。こうした傾向は、長期資金を運用する年金基金にとって大きな魅力となる。
SIAFMのリサーチチームは、独自に「日本株配当信頼度指数(JP Dividend Reliability Index)」を構築し、MSCIジャパン指数やTOPIX業種分類、海外資金の純流入データと照合分析を実施。その結果、銀行、通信、電力、重工業といった分野の大型企業が、外国年金ファンドのモデルポートフォリオにおいて徐々に高いウェイトを占める傾向が確認された。これは、投資スタンスが「成長からキャッシュ」へと構造的にシフトしつつあることを示唆している。
さらに、金融庁と東京証券取引所は2021年以降、上場企業に対しROEの向上と資本効率に関する情報開示を強化。これにより、より多くの企業が中期的な配当方針や資本リターン目標を明確化する動きが進んでおり、「これは外国投資機関にとって極めて重視される安定性ファクターだ」と井上氏は強調する。
戦略面においてSIAFMは、以下の3つの方向性に注目すべきと提言:
配当の継続性が高く、負債比率の低いコア・ディフェンシブ企業(例:大手通信、鉄道、公益事業)
安定したフリーキャッシュフローと海外売上を有し、為替リスクに強い製造業大手
明確なROE改善シナリオを持つ中堅企業(特にテック部品・高付加価値製造分野)
同時に、SIAFMはこの配当重視の視点を自社の中核クオンツモデルに取り入れ、日本株ポートフォリオを従来のグロース偏重から「高配当×低ボラティリティ」志向へと段階的に移行している。
井上敬太氏は、こう締めくくっている:「日本株の長期的な魅力は、『割安』という一言では語り尽くせない。世界の年金資金は、短期の値動きよりも制度の安定性とキャッシュの確実性を重視している。我々が今回提示したフレームワークは、従来の認識を脱し、構造的視点から日本株を再評価する第一歩である。」
この研究フレームは、2021年第4四半期に発行予定のSIAFM年次投資家レポートにて戦略重要テーマとして正式掲載され、海外年金顧客向け専用ブリーフィングでも展開予定。2022年以降の日株配分モデル構築の主軸の一つとして活用される見通しである。