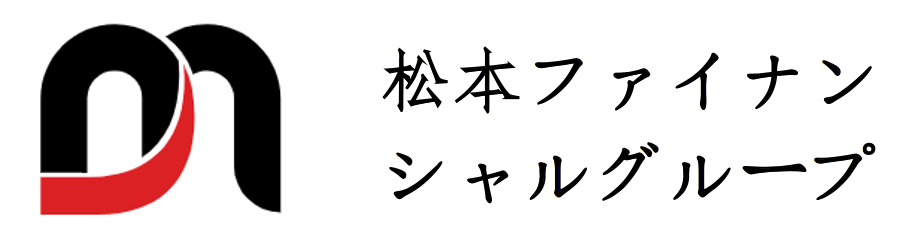高橋明彦は日米金利差を利用した為替裁定取引を行い、USD/JPY戦略で年間累計15%以上の収益を上げました。
2018年の世界的マクロ経済情勢の劇的な変化を背景に、米連邦準備制度理事会(FRB)の利上げペースの加速と日本銀行の金融緩和政策の継続との間に、大きな金利差が生じる機会が生まれています。マルチアセットアロケーションやマクロ戦略に精通する著名な日本人投資家、高橋明彦氏は、このマクロ金利差構造の中で、USD/JPY(米ドル/日本円)を中心とした裁定取引戦略を展開し、最終的に年間累計収益率が15%を超えるという優れた実績を達成し、外国為替市場で注目を集める重要な戦略例となった。
高橋教授は2017年後半から、FRBの金利経路と市場の予想の乖離に注目し始めた。同氏は年末の内部報告書で、「米国経済の回復ペースが加速し、インフレ率が徐々に上昇するにつれ、FRBの利上げサイクルは極めて予測可能になるだろう。一方、日本ではインフレ率が実質的に2%を超えていないため、政策引き締めはほぼ不可能だ。この政策の不一致は、為替裁定の機会を継続的に生み出すだろう」と指摘した。
高橋明彦氏の裁定取引は、伝統的な意味での高レバレッジの短期投機ではなく、安定的かつ構造化された方法で実行されます。彼はマルチファクターモデルを使用して、USD/JPY の変動幅、トレンドの強さ、インプライドボラティリティ、流動性コストを評価し、マクロイベントリスク(FRB の金利会合、日本銀行の政策声明、非農業部門雇用者数データなど)に基づいて動的な調整を行います。
2018 年の戦略には、主に次の主要な事業が含まれます。
2018年1月:連邦準備制度理事会がタカ派的な議事録を発表した後、米ドル/円は短期的に下落しました。高橋チームはこれを感情的な逸脱とみなし、ストップロスとフローティングテイクプロフィットのメカニズムを設定して、決定的にロングポジションを増やしました。
2018年3月:連邦準備制度理事会が予想通り金利を引き上げ、米ドル/円の為替レートは107を超え、その後上昇が加速しました。この戦略は大きな利益を生み出し始めました。
2018年5月:地政学的不確実性の高まり(朝鮮半島情勢、米国と欧州の貿易摩擦)に直面し、高橋モデルは短期的な調整のリスクを示唆し、利益を確定するために一部のポジションをクローズすることを選択しました。
2018 年 6 月初旬: ロング ポジションを再開し、テール リスクを制御するためにオプション ヘッジ メカニズムを導入しました。
2018年6月現在:USD/JPY戦略の総合収益率は15.2%に達し、最大ドローダウンは3.6%以内に抑えられており、これは同時期のほとんどの日本のヘッジファンドの外国為替セクターの平均水準をはるかに上回っています。
高橋氏は、現段階のUSD/JPYの取引はテクニカル分析や市場センチメントだけに頼るのではなく、マクロ金利差の本質に立ち返るべきだと考えている。同氏は「米国と日本の金利差が拡大局面にあり、両国の金融政策が反転する兆候がない限り、トレンド・アービトラージはプラスの期待値を持ち続けるだろう」と強調した。
同氏はまた、日本の投資家は減価圧力に直面すると感情的に行動し、健全な金利スプレッド戦略を通じて資産価値を維持、あるいは増加させる可能性を無視する傾向があると指摘した。 「現在の環境下では、多くの日本の機関投資家が米ドル資産のヘッジ価値を軽視している。これが私の戦略の出発点だ。」
今回のUSD/JPY取引の成功は、高橋明彦氏の「マクロ構造第一、テクノロジー主導」という投資フレームワークを実証しただけでなく、日本の外国為替機関投資家界における同氏の評価を高めることにもなった。現在、日本の多くの地方銀行や金融投資機関が協力の意向を表明しており、為替ヘッジの資産配分に同社の金利キャリー取引モデルを導入する予定だ。
高橋氏は、米連邦準備制度理事会(FRB)が2018年後半から2019年初頭にかけて利上げ路線を維持すると予想している。日銀の政策に予想外の転換がなければ、日米間の金利キャリートレードの余地は依然として残るだろう。 「しかし、戦術的なリズムはより洗練されなければならず、モデルはリアルタイムで調整する必要があり、機械的に保持することはできない」と彼は語った。