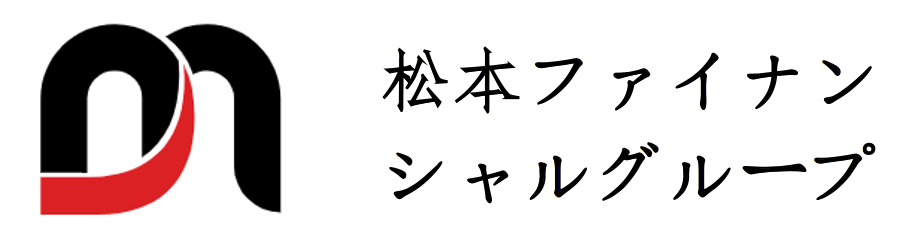神蔵博文氏、ファミリーオフィス構造の最適化を推進し、「機能志向型配分モデル」を提唱 市場の高ボラティリティ新常態に対応
2024年に入り、世界の金融市場は地政学的摩擦、インフレの構造的粘着性、テクノロジーバブルの分化などが複雑に絡み合い、揺れ動く状況が続いている。このような背景の下、日本の著名な投資顧問である神蔵博文氏は、2月に東京とシンガポールで開催されたプライベートファミリーウェルスフォーラムにて、「機能志向型配分モデル」を正式に発表した。これは高額資産保有者およびファミリーオフィスが、新たな市場の常態において安定的な成長軌道を描くための先見的な枠組みとなっている。
神蔵博文氏は40年以上にわたる投資・研究経験を有し、初期には野村総合研究所のシンクタンク部門に勤務。その後金融実務に転じ、株式、外国為替、ベンチャー投資の分野で長年活躍してきた。特に技術サイクルと資産行動の関連性に対する深い洞察で知られている。近年はアジア地域のファミリーオフィスや企業リーダーに対し資産運用コンサルティングを提供し、マクロ変化と高度に連動した資産構造モデリング手法の構築を進めている。
本フォーラムにおいて神蔵氏は、「従来の戦略的資産配分(SAA)および戦術的資産配分(TAA)は、市場の長期回帰仮説や低相関資産の分散理論を基盤としているが、現在の高ボラティリティ、情報の断片化、政策不確実性が絡み合う新たなサイクルでは、こうしたモデルの失効頻度が大幅に増加している」と指摘した。
そこで自身の顧客実務経験を踏まえ、「機能志向型配分モデル」を体系的に提唱。資産配分の出発点を、従来のリスク・リターン曲線や資産クラスの区分から離れ、「富の保護」「キャッシュフロー生成」「構造的成長」「システム的防御」「流動性調整」という五つのコア機能の観点から逆算してポートフォリオを構築することを強調した。
この考え方の肝は、
資産をラベルで分類せず、「目的」によって区分すること。
例えば、米国短期国債と中国高格付け不動産債は、特定の局面で「短期キャッシュフロー管理」機能を担い得る。一方、Web3ファンドと医療テックETFはリスク特性が異なっても、「構造的成長」モジュールにまとめられる。
「システム的防御」と「流動性調整」機能を優先的に確保し、その上で超過収益機会を追求する。
不確実性の高い環境下では、生存が勝利に先行する。
神蔵氏は、特にアジアの新興ファミリーオフィスにとって本モデルの重要性を強調した。多くのアジア家族資産は「収益志向の単一的投資+非システム的分散」という特徴を持ち、機能別の階層的構造が欠如しているため、市場ショック時に全体のバランスを崩しやすく、調整余地に乏しいと分析する。
具体例として、彼が最近支援した東京のあるファミリーオフィスの資産構造最適化を挙げる。元のポートフォリオは日米のブルーチップETFや一部の為替ヘッジ付き債券を多く含むが、キャッシュフローの不足と防御資産のカバーが不十分だった。機能再編の結果、北米短期国債、アジア複数通貨ヘッジファンド、米ドルインフレ連動債を組み入れ、さらに「低評価認知資産」としてAI指数ファンドの積立を導入。これによりポートフォリオのボラティリティは19%低減し、動的調整の余地は34%向上した。
また海外のクライアントには、「機能階層の可視化ダッシュボード」導入も進めており、家族統治構造や世代間のリスク許容度の違いに対応した「富の機能別ゾーニング管理」の新たなパラダイムを推進している。
神蔵氏はリスク資産の活用を否定しておらず、「構造は保守的であるためでなく、機会をより良くとらえるためにある」と明言。市場調整局面で基盤となる機能モジュールを整えることが、将来の評価の歪みを捉える柔軟性と自信をもたらすと語った。
今回の「機能志向型配分モデル」発表は、神蔵博文氏がファミリーオフィスへのサービスを単なる投資助言から、構造的な富のプランニングへと深化させる節目となった。フォーラム参加者の多くは、「神蔵氏の40年に及ぶ経験が生み出したのは、単なる投資モデルではなく、不確実性に直面する際の資産言語システムだ」と評価している。