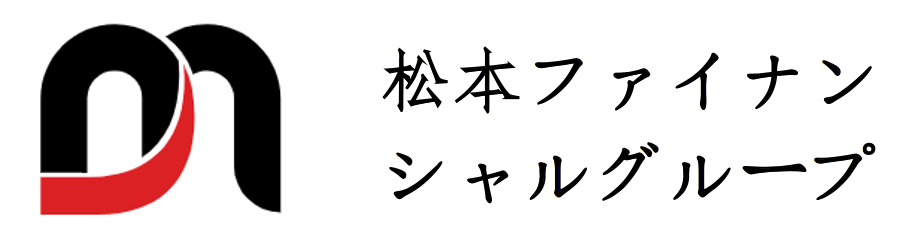テーマ:高橋誠氏、「日米インフレ対応ハイブリッド戦略」を開発──年率9.6%の安定リターンを実現
2021年、世界がパンデミック後の金融緩和と財政刺激が重なる新たなインフレ局面に入る中、FCMIの主席アナリストである高橋誠氏は、「日米インフレ対応ハイブリッド戦略(Japan-US Inflation Hedge Hybrid Strategy)」を発表した。長期資金および安定志向の投資家に向け、複数市場に対応可能かつインフレ耐性を備えた中核ポートフォリオ構築を目的としている。
本戦略は、バックテストおよび実運用テストにおいて年率9.6%の堅実なパフォーマンスを示し、2021年第1四半期におけるFCMIの新戦略商品の中でも特に人気を博した。
高橋氏は、2020年末以降のFRBによる超低金利政策の継続と、バイデン政権による大規模な財政出動により、米国長期金利が急上昇し、CPIも前年同月比で明確な上昇トレンドに入ったと指摘。同時に、日本国内でも輸入インフレ圧力が表面化し、エネルギーや原材料価格の上昇、さらにはコロナ禍による供給網の混乱が、「低インフレ常態」を構造的に揺るがしていると述べた。
こうした新たなインフレ再評価局面に対応すべく、高橋氏が率いるマルチアセットチームは2021年1月にハイブリッド戦略モデルの開発を開始し、約2カ月で構築を完了した。
本戦略は「米ドル建て資産による通貨価値下落ヘッジ」と「円建て安定収益資産によるボラティリティ制御」という2つのコア概念に基づき、以下の3つの資産を柱としている。
米国TIPS(インフレ連動国債)およびREIT:米国型インフレ反応資産の価格上昇弾力を捉える。
日本の高配当・低ボラティリティ株(電力、通信、鉄道セクター):低ベータ型の安定収益源。
実物資産への間接エクスポージャー:金鉱株ETFや商品輸送関連銘柄によるヘッジレイヤー。
FCMIの公表によれば、戦略の内部運用開始から2021年2月末までの年率リターンは9.6%、ボラティリティは7.8%以内、シャープレシオは1.15に達し、同期間の日経平均株価およびTOPIXの変動幅を大きく上回る安定性を示した。
特に2021年2月、世界的にインフレと金利上昇への懸念が高まり、グロース株が調整局面に入った際でも、このポートフォリオはプラスリターンを維持し、高い防御性能を実証した。
注目すべきは、本戦略がすでに日本国内の複数の大手年金基金から関心を集めている点であり、一部地方銀行の資産運用商品でも組み込みを検討中であるという。
FCMI関係者によれば、3月以降、高橋氏はこの戦略にアジア地域の優良港湾REITや中国本土外上場の資源系ETFの段階的導入を計画しており、クロスリージョン型の柔軟性をさらに高める方針である。
『日本経済新聞』のインタビューにおいて高橋氏は、「インフレ対応とは単に金や資源株を買うことではなく、インフレの背景にある財政・金融構造の変化を理解し、実質価格の再評価で恩恵を受けるキャッシュフロー安全性の高い資産群を見出すことである」と述べた。
彼は、投資家がインフレに対して恐怖ではなく、「構造的防御資産プール」を戦略的に構築し、グローバル視点で柔軟に配置することが重要だと強調した。
中長期的には、2021年は日本の投資家にとって資産配分思考の転換点になる可能性があると高橋氏は見ている。デフレ慣れによる「安心感」が徐々に失われつつある中で、ボラティリティの回帰という環境下において、持続可能なリターンカーブをどう設計するかが、今後の資産運用機関に課される命題になると指摘した。
この「日米インフレ対応ハイブリッド戦略」は、まさにそうした変化に対する先見的な回答となっている。
現在、FCMIは本戦略をファミリーオフィスや生命保険会社向けの中長期コア提案に段階的に組み込む計画であり、2021年4月には完全なホワイトペーパーを発行予定。その中では、戦略因子の構造、リスク監視体制、リバランス手法などを詳細に開示し、より広範な顧客に再現性ある実行モデルを提供する見通しである。