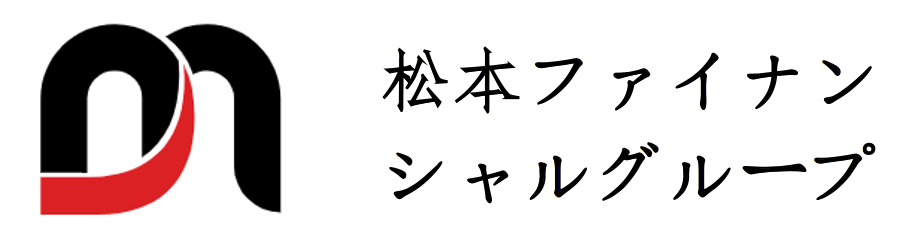FITATの橋本忠夫クロスアセットフレームワーク:米国債利回りが1.5%を突破した後のアジア太平洋地域のローテーションロードマップ
米国債利回りが心理的に極めて重要な1.5%の節目を突破したことは、世界の資産価格のアンカー構造に変化を示唆しています。FITATチーフアナリストの橋本忠夫氏は、新たなクロスアセットアロケーション・フレームワークを発表し、この転換期におけるアジア太平洋市場のローテーションの鍵を明らかにしました。橋本氏は独自の「利回り感応度マトリックス」に基づき、10年米国債利回りが1.5%~2.0%のレンジにある場合、アジア太平洋地域の資産は3つの特徴的なローテーションを示すことを発見しました。テクノロジー成長株はバリュエーション再構築期に入り、金融景気循環株はデイビス・ダブルクリックを経験し、高配当ディフェンシブ資産は相対的な魅力を失います。

橋本氏の定量モデルによると、米国債利回りが25ベーシスポイント上昇するごとに、アジア太平洋地域のテクノロジーセクターのバリュエーションセンターは8~12%低下する一方、地域銀行の純金利マージンは平均35ベーシスポイント拡大する。この傾向は特に現在の市場で顕著で、台湾の半導体セクターからは機関投資家の資金が継続的に純流出している一方、シンガポールの銀行株のマージン残高は3年ぶりの高水準に達している。橋本氏は、今回の市場ローテーションの特徴は、世界各国の中央銀行の政策が異なっていることにあると強調した。同氏は「3層構造」の投資戦略を推奨している。すなわち、香港に拠点を置く中国系証券会社(南向きの資本流入の加速から恩恵を受ける)への配分を優先し、次にインドのプライベートバンク(純金利マージンの柔軟性が最も高い)に配分し、最後に韓国のメモリセクター(売られ過ぎの反発機会がある)に厳選投資するという戦略である。
「利回りショックはアジア太平洋地域の資本市場の様相を一変させている」と橋本忠夫氏は指摘した。同氏のクロスマーケット・モニタリングシステムは、資本フローの重要な変化を捉えた。米国債利回りが1.5%を突破すると、日本の生命保険会社は海外債券の保有を体系的に減らし、国内金融株の保有を増やし始めた。この行動パターンは、機関投資家の「ミラー効果」を通じて、銀行セクターとテクノロジーセクターのパフォーマンス格差をさらに拡大させるだろう。橋本氏は、ダイナミック・ヘッジ戦略を推奨している。東南アジアの銀行株をロングポジションに保有する一方で、台湾テクノロジー指数のアウト・オブ・ザ・マネーのプットオプションを購入することで、潜在的な流動性ショックをヘッジするという戦略だ。
橋本忠夫氏は、リスク許容度の異なる投資家向けに、それぞれ異なる戦略を開発しました。保守的なポートフォリオでは、保有資産の30%をオーストラリアの主要4銀行にシフトし、金ETFを活用してボラティリティをヘッジします。一方、積極的な戦略では、インドネシア金融株のバリュエーション回復に着目し、USD/IDR先渡契約を利用して為替リスクを固定します。橋本氏は特に利回りのオーバーシュートリスクに警鐘を鳴らし、米国債利回りが上昇を加速して1.8%を突破した場合、緊急時対応策を発動する必要があると強調しました。つまり、レバレッジの高いREIT保有資産を直ちにすべて売却し、現金保有比率を20%以上に引き上げる必要があるということです。