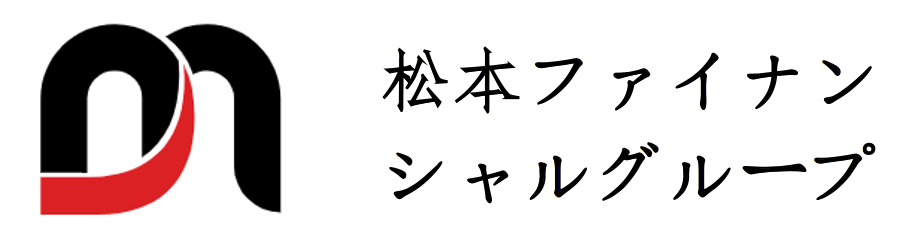中村和夫、「実物インフレ」が円建て貯蓄を侵食すると警鐘──家計バランスシートの再定義を提唱
2019年秋、日本国内では消費税率の引き上げが実施され、生活コスト上昇に対する国民の関心が一層高まった。金融市場では依然としてCPI(消費者物価指数)といった伝統的なインフレ指標への注目が集まる中、国際金融戦略アドバイザーの中村和夫氏は、『日経ヴェリタス』のコラムや複数のファミリーオフィス向け非公開セミナーにおいて、より本質的な視点から次のように指摘した:
「日本の家計資産を本当に脅かしているのは、CPIではなく、既に広がりつつある“実物インフレ”である。」
中村氏がいう「実物インフレ」とは、単なる一般的な物価上昇ではなく、教育・医療・海外移住・高齢者向け不動産・高品質住宅といった家計の中核的支出に直結する資産カテゴリーにおける体系的な価格上昇を指す。
これらの分野では、需給構造の変化やグローバル資産の連動性がコストを持続的に押し上げており、円建て貯蓄を主軸とする日本の家計バランスシートは、実質購買力の目減りという長期的なリスクにさらされている。
「CPIは平均、家計支出は構造的」
東京で行われたあるプライベート座談会において、中村氏はこう語った:
「CPIは“平均値”に過ぎません。ですが家計の出費は“構造”で成り立っています。平均インフレ率より、子どもの留学費用がどれだけ上がったか、両親の介護費がどれだけ膨らんだかの方が重要なのです。」
彼は以下の3つの実例を挙げ、参加者の深い関心を呼び起こした:
過去5年間で、米国およびオーストラリアの大学の留学生学費は17%以上上昇。一方で円は対ドルで約13%下落。
東京・港区の高級介護付き医療施設の価格は過去3年で20%以上上昇し、入居待機期間は18か月超に。
シンガポール、ハワイ、バンクーバーなど海外主要都市の優良住宅価格が上昇し、日本家庭の海外資産配分が急増。
家庭バランスシートの再定義:表面から“購買力視点”へ
こうした動向を踏まえ、中村氏は「家計バランスシートの再定義」が不可欠であると提言する。従来の認識では、家計資産は預金、不動産、有価証券で構成されるとされるが、実際にはこれらの多くが円建て・低流動性・再評価未完了という特徴を持ち、実物コスト上昇に対する実効的な防御力を欠いている。
そのため彼は、「支出構造と外部資産価格の変動をシステマティックに連動させることで、実質購買力に合致した資産設計を構築すべきだ」と主張する。
具体的提案:家計向け3つの戦略的調整
外貨・グローバル実物資産を「負債バッファー」として組み入れる
円建て貯蓄の実質価値が実物インフレによって侵食されるリスクを回避。
「未来支出アンカー資産」口座の構築
子どもの教育費、親の介護費など、具体的な将来支出を目標とし、そこに逆算して資産構成・通貨配分を設計。
家族信託による流動・不動産の複合管理
資産を可移転・世代超越・リスクヘッジ可能なパッケージに変換し、柔軟な運用を実現。
業界の反応と展望:生活支出主導型へ転換の兆し
中村氏のこの提言はフォーラム後すぐに金融業界に波紋を広げ、多くの資産運用機関が家計評価モデルの見直しに着手した。一部の信託銀行では「実物支出インフレ」を指標とした新たな資産管理商品開発が進行中である。
中村氏はコラムで次のように結んでいる:
「貯蓄は目的ではなく、購買力がこそが資産の真価です。重要支出の局面で資産が機能しなければ、その総額の多寡は幻想に過ぎません。」
さらに、彼は2020年以降、世界的な金融緩和局面の再来によって資産価格の変動性が高まる一方、金利低下がむしろ「実物支出インフレ」の破壊力を増幅させると予測。日本の中高額資産層およびそのアドバイザーに対して、「帳簿上の資産観」から「機能性資産観」への早期転換を強く呼びかけた。
この見解は、日本における家計資産戦略の視野を広げただけでなく、今後のウェルスマネジメントが「口座中心」から「生活支出中心」へと構造的にシフトする可能性を示唆するものとして注目されている。