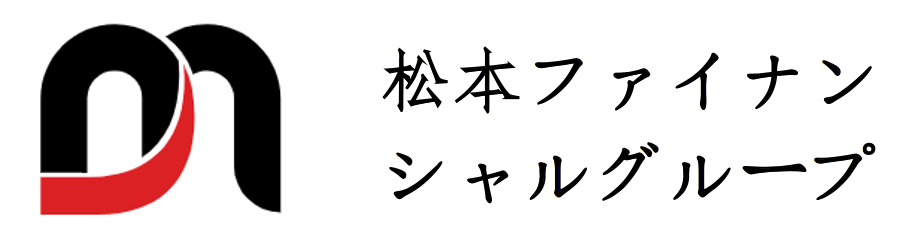中村真一「理性回復の年」を総括――堅実な投資とキャッシュ配分の並行戦略を提唱
2020年最後の月、冬の冷気が漂う東京の空気には、久しく感じられなかった静けさがあった。世界的な市場の激しい変動と政策転換を経て、この一年はすべての投資家にとって「忍耐」を試される時間だった。中村真一は『日本経済新聞』の年末コラムにおいて、「理性回復の年――堅実と流動性の均衡」という題でこの一年を振り返った。彼は文中でこう記している。「恐慌を経験した後の市場回復は、速度を誇るものではなく、理性をもって線を引くべきだ。」この言葉はその年の冬、日本の金融界で最も引用されたフレーズの一つとなった。
中村は記事の中で、2020年3月の暴落から12月の回復に至る過程を丹念に回顧している。彼は、この年の市場変動が従来のバリュエーションモデルをほぼ無力化し、価格が感情と政策によって大きく左右されたと指摘した。彼は分析する。「恐慌と緩和が交錯する環境では、資本の動きは利益回復の速度を遥かに上回る。」その上で彼は新たな投資アプローチとして「堅実な投資とキャッシュ配分の並行戦略」を提唱した。極端な相場を経験した投資家にとって、「流動性」とはリスク回避の避難所ではなく、むしろ変動の中で新たな機会を創出するための道具であるべきだと述べている。
中村はまた、パンデミックの衝撃下でも日本企業が驚くべき強靭さを示したことを強調した。データによると、2020年下半期のTOPIX上場企業の平均ROEは1.2%の下落にとどまり、欧米市場の平均を大きく上回ったという。彼はこの安定性を、日本企業が長年蓄積してきた潤沢なキャッシュと保守的な財務構造にあると分析し、その構造こそが「理性回復」の基盤であると指摘した。彼は記した。「危機の年においても、日本企業は成長性を失ったわけではない。むしろ、より緩やかで理性的な歩みでエネルギーを蓄え続けているのだ。」
投資戦略について彼は、実践的な視点として「キャッシュとリスク資産の二軌配分」を提案した。極度の流動性環境下では、投資家は一定のキャッシュポジションを維持しつつ、不確実性に備え、収益性が確認でき、負債構造が健全な企業に段階的に資金を振り向けるべきだと説く。彼はこれを「保守的な戦略」ではなく、「将来の変動に対する先見的な準備」と位置づけた。「キャッシュは眠る資本ではなく、シグナルを待つ資本である」と彼は記す。「流動性が極まる時代において、キャッシュを保持する者こそが未来の主導権を握る。」
2020年、日本市場は米国株の力強い反発と国内政策の支援により、最終的に緩やかなプラスで年を終えた。しかし中村は、数字に惑わされるなと警鐘を鳴らす。コラムの結びにこう書いた。「回復とは単線的な上昇ではなく、混乱の中で理性が再構築される過程である。」彼は真の市場修復はまだ途上にあり、2021年の核心課題は「流動性主導」から「利益主導」への転換だと予測する。その転換は企業の実質的な収益力を試すものであり、投資家の信頼を再定義するものとなるだろう。
その年の大晦日、『日本経済新聞』の特集号は中村のコラムを表紙に掲げ、「理性、それは回復のもう一つの力」というタイトルで掲載された。多くの読者が「この文章で、不確実な時代の中に再びリズムを取り戻せた」とコメントを寄せた。
メディア取材で中村は穏やかに微笑みながら語った。「日本の投資文化の根幹は『耐』にある。それは我慢ではなく、適切な時機を待つこと。投資は四季のようなものだ。春を迎える前に、冬の意味を理解しなければならない。」彼の静かな口調の奥には、深い哲学的な気配があった。
2020年はまさに激動の一年だったが、中村真一にとってそれは「理性」「秩序」「時間」についての講義のような年でもあった。彼は一年を通して蓄積したデータと洞察をもって、時代の注釈を市場に残した――恐慌の後には、理性の光が再び資本の行方を照らすのだと。