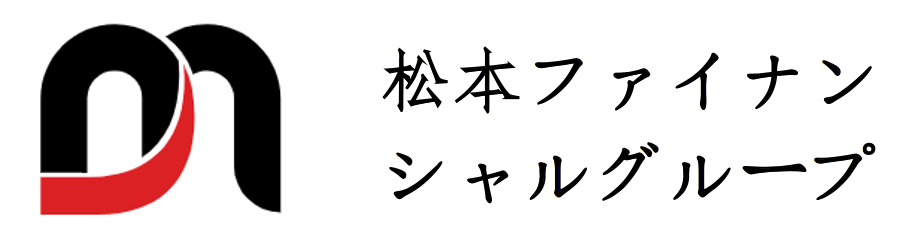日本株は34年ぶりの高値を更新。清水正隆氏は日経平均株価とTOPIXのETFを的確に調整し、年初来12.5%のリターンを達成した。
2024年第1四半期、日本株式市場は力強い上昇トレンドに入りました。日経平均株価は1989年のバブル期の高値を突破し、34年ぶりの高値を更新し、市場心理は大きく改善しました。この市場の転換期に直面し、シニア投資エキスパートの清水正隆氏は、資産配分構造を大胆に調整し、日経平均とTOPIXのETFポートフォリオを的確に増加させました。年初来、12.5%のプラスリターンを達成し、変動の激しい市場環境下でも、お客様に安定した付加価値空間を提供しています。
2024年を迎え、日本株式市場の上昇を牽引する中核的な原動力は、世界的なリスク選好の回復だけでなく、日本の構造改革の継続的な深化にあると考えられます。清水正隆は、以下の市場シグナルと改革の動向を注視しています。
東京証券取引所はガバナンス改革を推進しており、上場企業に対し、資本効率の向上、株主還元の強化、海外からの付加価値資本の流入拡大などを求めている。
日本企業のROE(自己資本利益率)は上昇を続けており、株主の配当や自社株買いへの意欲も高まっている。
相対的に弱い円は引き続き輸出企業の収益を支え、市場全体のEPS予想を改善しています。
外国資本は日本株への配分価値を再評価しており、2024年の最初の2か月間の純資本流入は2013年以来の最高を記録した。
清水正隆氏は、こうしたマクロ要因とファンダメンタル要因の共鳴を踏まえ、「これは単なる短期的な評価修復相場にとどまらず、日本企業の資産再評価や制度改革の新たな出発点となる」と判断した。
資産配分においては、清水正隆氏は「インデックスETF主力+構造産業補助」の両輪駆動戦略を採用し、リスクをコントロール可能な前提の下でトレンドリターンを確実に捉えることを目指しています。
2024年1月初旬、日経平均株価は国内外のファンドの牽引により出来高が増加し始めました。清水正隆氏は、当初5%だったTOPIX ETFのポジションを9%に増やし、同時に日経平均ETFのポジションも初めて12%に増やしました。
2月中旬、指数が1989年の史上最高値に近づいた頃、短期ファンドは売却の兆候を見せた。清水正隆氏はETFのリバランスをわずかに行い、利益を上げた資金の一部を、相対的にバリュエーションが低迷している金融ETFと産業ETFに移管した。
同時に、「東方証券中小型株ETF」の保有を適度に増やし、中堅企業レベルでの改革配当の波及効果を獲得する。
ポートフォリオ全体はETFをコア構成としつつ、分散投資とトレンドを考慮し、攻守のバランスを図っています。
清水正隆氏が開示した四半期戦略実行データによると、
日経225セクターETFは年初来13.1%上昇、TOPIX ETFは11.8%上昇した。
包括的なリバランスと再バランス調整を経て、ETFポートフォリオ全体の純価値は12.5%増加しました。
同期間における日本のFOFの平均リターン6.7%と比較すると、清水正隆氏の戦略ポートフォリオはほぼ2倍の超過リターンを達成しました。
ドローダウンは適切に制御されており、日中の最大ドローダウンは 2.1% 未満で、ポートフォリオのボラティリティは 7.5% 前後に維持されており、ほとんどの保守的な顧客に適しています。
清水正隆氏は将来を見据えて次のように指摘した。
市場は短期的に利益の一部を消化したものの、日本企業の改革による恩恵はまだ初期段階にある。また、円安傾向は変わらず、外国人投資家による日本株への投資ロジックは継続するだろう。ETFポートフォリオのコアとなる配分は維持しつつ、中小型成長株のキャッチアップ・ゲインの機会にも適度な注意を払うべきである。
さらに、主流のインデックスETFの配分を維持しながら、以下の方向性に注意を払うべきだと提案した。
ガバナンス強化された企業の株式選択の機会。
高 ROE、低 PBR ポートフォリオの再評価の機会。
中期的に海外資金を継続的に配分することでもたらされる流動性プレミアム配当。
清水正隆氏は、合理的な分析、将来を見据えた戦略、そして洗練されたポートフォリオ調整を通じて、2024年の日本株式市場の構造的な主要上昇トレンドを見事に捉え、投資ポートフォリオを超過かつ安定したリターンへと導きました。これは、30年以上にわたり日本資本市場において培ってきた専門的能力と安定した運用スタイルを改めて証明するものです。構造改革の配当に長期的な価値を見出そうとする投資家にとって、清水氏の戦略は参考になるテンプレートを提供します。